司馬遼太郎は代表作「坂の上の雲」や「菜の花の沖」書きながら”北アジア史的なもの”を考え続けている。それが「ロシアについて 北方の原形」の作品になった。
大阪外語蒙古学科を出た司馬さんは、<シベリアには森林(タイガ)や河川で原始的な狩猟採取の生活をしているひとびとだけでなく、大小の遊牧集団も住んでいた。その最大のものが、バイカル湖畔に遊牧するブリヤート・モンゴル人だった。低地モンゴル人といってもいい。だからモンゴル高原のモンゴル人(古沢注記=高地モンゴル人)とは、別に考える必要がある。>と述べた。
さらに<バイカル湖を中心に展開する高地には、古代中国の視野に、丁霊、堅昆、高車といった諸遊牧国家が存在していた。やがてかれらは匈奴に屈服し、併合された。(中略)バイカル湖西方のイエニセイ川右岸草原にミヌシンスク遺跡が発見され、これによってシベリアに紀元前三〇〇〇年というふるい時代に西方のオリエント文明の影響をうけた青銅器文化が存在していたことがわかった。>と指摘している。
荒れる姿をみせたバイカル湖
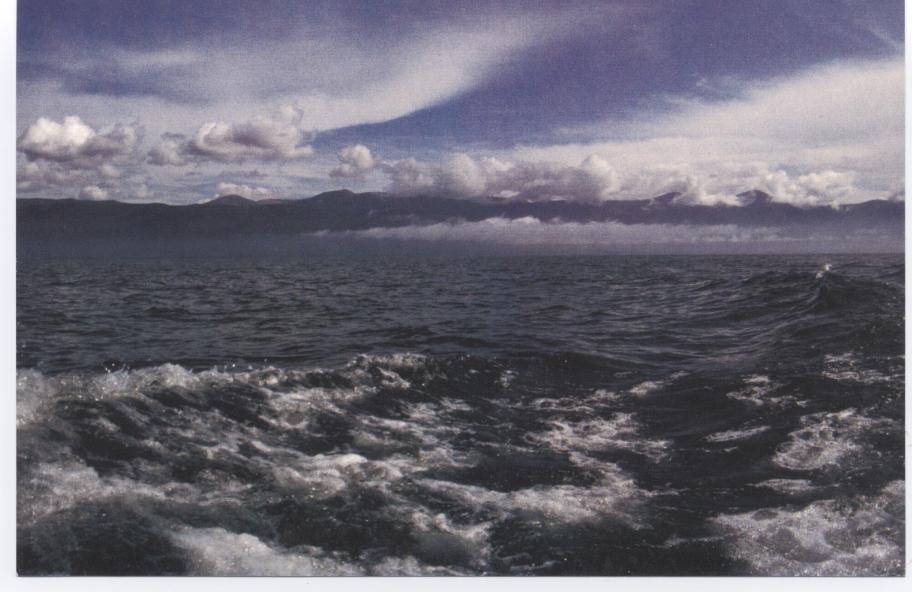
「ロシアについて」は1986年の作品だが、その後2001年に佐賀医科大学がDNA鑑定によって「日本人はバイカル湖畔のブリヤート人との共通点が非常に多く、朝鮮人、南中国人、台湾人などと共通する特徴を持ったのが各1体だったのに対して、ブリヤート人とは17体近くが共通していた」と発表した。
北方系日本人のルーツがシベリアのバイカル湖にあるということが科学的分析で立証された。
大胆な想定をすれば、バイカル湖周辺は約二万年前に人もマンモスも住めない極寒の時代を迎えて、ブリヤート人暖かい土地を求めて東進を始めた。この人たちは一万三千年前には、シベリアのアムール川周辺に到達し、さらに地続きのサハリン、北海道を経て、まず本州の津軽地方に姿を現した。
この一万三千年前というのは地球が氷河期から温暖期に入る境目の時期になる。日本列島に渡ったブリヤート人は海を渡ってシベリアの大地に戻るよりも日本列島を南下し、縄文人の祖先となったと考えるのが妥当であろう。
さらに想定を重ねると氷河期のブリヤート人は東進する道のほかに、南下する道もあったのでないか。そこには極寒であったかもしれないが、夏には草地が甦るモンゴル平原が広がっている。
それが匈奴の祖先である丁霊、堅昆、高車といった遊牧国家となりモンゴル帝国を築いたのではないか。史料が乏しい古代史には推理小説を読み解くような楽しさがある。
だが北アジア史のほとんどが未解明だといえよう。いずれも文字を持たない草原の遊牧国家であった。高車、丁零の呼び名は、漢字文化を持った「魏書」や「北史」にわずかに出てくるに過ぎない。
